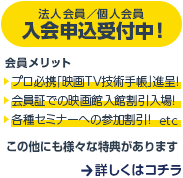2024年度 東北支部 ミニセミナー 報告
-
日時:2025 年3 月23 日(日)13:00〜17:00
会場:NHK 仙台放送局 T-1 スタジオ
共催:一般社団法人 東北映像製作社協会
カメラは魔法の玉手箱~テクとアイディアを磨く
めまぐるしく進化する映像機器に、どれだけ追いついていけているだろうか。気づけば、横文字がいくつも並ぶメニュー画面に戸惑いを覚える日々。四角い箱にレンズがついただけなのに、これほどまでにてこずらせるのかと。それでも知ればきっと魔法の玉手箱になるはず。以下、簡単な報告まで。
第一部 視聴検討 「それぞれの作品から学ぶ・カメラマンマインドの形」

「震災後の街に生まれた語り部の思い」
小野 実央 (NHK 仙台局 映像取材)仙台局初任 福島県浜通り出身
(小野) タイトルの通り、気仙沼で震災後に産まれた小学生が語り部をしていると聞いて、彼の眼に自分の町がどう映っているのかなって、なんで知らない震災のことを語ってみようと考えたのか、そんなことを知りたくてリポートにしました。
【V 視聴・概要】
気仙沼市の震災遺構で語り部活動をしている小学生は、震災後に産まれた12 歳。新しい公園や道路ができ、嬉しかったと語る。学校の防災学習などを通じて興味を持つようになった。「信じられない出来事、だからこそ伝えていきたい」「正しい情報を若い安く伝えたい」と。伝承施設の職員は「経験した大人が語り継いでいく時間は限られている。震災を知らない世代が語り継いでいくことはとても大切」と語った。
【トーク】
(参加者A) 震災をイメージさせる荒れている海を使わず、穏やかな海が印象的。
(小野) いつも海が穏やかなので、本当に津波が起こったところなのか、伝わるのかどうか。黙とうの意味を問う場面で、背中越しの海が印象的ではあるけど、結局ただの風景になっている気もして、ちゃんと伝わったのか。
(参加者N) ちょっと厳しい意見になりますが、おそらく「ここに立って」とお願いして撮っているカット。すごく不自然な印象にも。もっと自然な感じで、気仙沼の風景と彼を絡めて撮れたら良かったのかなと。
(小野) 「立ってください」は、私も嫌い。でも、どうしても編集上必要だからと撮ってしまう。いい感じにその場にいてもらうことがすごく難しい。そこもインタビュー終わりに「風景を撮るから、そこにいて」って感じで。編集の時も、違和感があると言いながら、そのまま。難しかったです。ここに立ってくれれば、という映像的な企み、欲しい映像と、お願いはしたくない、という思いがぶつかる。矛盾が出てきます。
(参加者N) 例えば、堤防で遊んでいる場面は自然と、その背景に震災の時になかった橋や防潮堤が入るはず。あまり不自然なのが出し方をせず、露骨しないという意味で。震災と海を関連づけて語りがちだけど、彼の中の動機にそれがあるかどうか、ひょっとしたらもっと他にも、自然に思いが出てくるような場があるのかも。
(参加者B) 小学生が語り部をする、彼ならではの語りはなかったか?大人の語り部のコピーだったら、ちょっともったいない。震災を知らないからこその、何か彼にしか語れない何か、特徴的な“語り”があれば。
(小野) そこが難しかった。彼はまだ「何を伝えたいか」という前に、まず「正しく、間違えずに伝えたい」だったので、彼なりのこだわりが、あれば良いとも思ったが、少し考え直して「正しく分かりやすく伝えるだけでも、大変なことだし、淡々と語るだけじゃなく、そこに意味を乗せられるようになることも大切なこと」かなと。最初は「3 カ所の震災遺構を回って、そこで語り部やってみたら?と声をかけられた」から、フワッとした感じ。何回か聞いてみたけど、「語り部が大事だと思うからです」ぐらいの答え。それだけで「やりたい」にならないはず、だからなぜそこまでやりたいのか、震災への興味が高まった理由を謎解きしていくような取材だった。そこが一番難しくて、たどり着けなかった。そのまま実感だけで放送したら、多分何も分からない。分かり易いストーリーを立てたら、実態と離れてしまうお恐れも。こちらの都合で、勝手に意味づけしてもいけないし、少年のいう言葉をそのまま文面通り伝えるだけでは、きっと伝わらない、伝えるって難しいなって。

(参加者Y) やはり私もよく、ストーリーの線がないと伝わらない、映像的興味だけではダメだと言われることが多い。でも興味を持ってやっぱり撮りたい、そんなジレンマがありますね。
(参加者G) 先輩の語り部の話を聞いてどんどん吸収していく、まだまだ成長過程なんだという印象。
(小野) 実はまだ反抗期の側面もあって、その優等生じゃない感も出したくて、現場に着いた時、何も言わずにドーンって車のドアを閉めるんですね。例えばそういう場面もあえて使うことでスーパーマンに映らない工夫をしてみた。
(参加者T) 確かにその場面で少し反抗期というか、まだまだ成長段階というか、そういう感じはしましたね。
(小野) 精神年齢も高く、大人受けのするON も言ってくれる。でも、そこに危うさがあるように思った。
(司会) どこまでが本音か、意図的にTV 向きな「良い話」をしてくれている可能性も。こちらの作った物語で、「少年語り部ヒーロー」に仕立ててしまったら、背負わなくてよいものまで、背負わせててしまう。
(小野) お母さんとは放送後、「語り部、続けなくてもね」みたいなことも話しました。「正しく伝わらないと意味がない」という彼に、「なんで意味ないの?」みたいな話を何度かしているうちに、しだいに、ギア(槍)がこちらに向いてくる気がした。そんな怖さもあって。こちらも彼のことを「正しく伝えなければ」って。
(司会) こちらの「なぜ?何で?」が、いつしか攻撃的な問いとして受け取られかねない。そこを避けるためにも、小学校の先生など、周りの大人の声もあると、もう少し輪郭が描けたかもしれないですね。
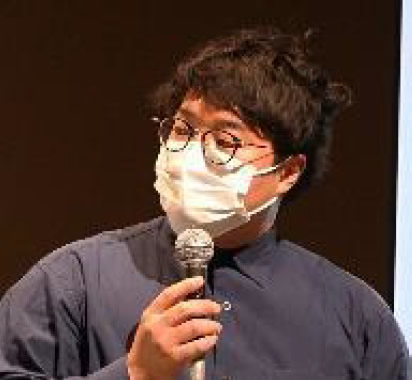
「射抜け勝利!東北学院高校女子弓道部」
齋藤 哲 (仙台放送エンタープライズ)2018 年入社、2024 年から報道カメラマンとして勤務
【V 視聴・概要】
東北学院高校女子弓道部は、創部2 年目にして新人大会優勝という快挙を成し遂げた。新チームは弓道を始めた初心者ばかり。礼に始まる作法から的に矢を命中させる技術の練習、大会までの様子を取材。しかし、大会では悔しい結果に終わる
【トーク】
(斎藤) 実は高校の時に弓道をやっていたこともあって、どんなスポーツか知らない人に、少し細部のところ、手元とか、アナログ的な道具、静寂さや緊張感も含めた弓道の格好いい部分を見せたいと思い冒頭をつないだ。選手の顔はあとで主人公として出てくるので、まずはスポーツとしての弓道を印象づけたいと。
(参加者L) あえて言えば、本番前の表情や所作の細部が入ると、手元に力が入る理由ももっと伝わるかなと。ちょっと、距離感がずっと一定なのが気になりました。
(斎藤) 私もその距離感が遠いなとは思いつつ。弓道がメンタルスポーツでもあり、当日の気分の浮き沈みによっても、ねらいが狂ったりするもの。初めての新人戦大会でもあり、近すぎると、影響があるんじゃないかというか、そういう距離感的な部分は悩ましかった。例えば、試合後の泣いてるシーンも、近くで撮りたかったが、先生と選手たちだけで完結させてあげたい、という気持ちもあった。試合中は他校の生徒もいるので、中には入れず。時間によっては、声かけできない制約もあるので、近い距離で撮ったほうがいいと思いつつ、難しかった。
(参加者L) 確かに、本番時はもちろんのこと、制約や気遣いがあるだろうと思いますが、練習の時など、近づけるタイミングもあったのでは。
(斎藤) 先輩が後輩を教えてるような場面であれば、大丈夫ですが、選手の前に出てしまうと、思わぬ形で矢が飛んでしまうことや、弦が切れたときには、矢ではなく弓が飛んでくることもあって、入れないゾーンが大きい。それでも、近くに寄って撮る方法もあったと思う。心理的なところとも思うんですが、配慮しすぎたかなっていうところはありますね。
(司会) その後からの距離は決して遠くは感じない気もするけど、もっと近いところの、もっとアクセントとして強い絵があったらいいなっていうニュアンスですか?
(斎藤) 例えば、まだ慣れてない一年生は、弓を引くとき、余分な力が入り、力みがち、最後まで離せず、戻してしまうことも多いので、事故につながり易くあまり近か寄れない。手、同時にその体の使い方も大事なポイントなので、その時の表情も含め、もっと深く掘り下げていれば、1 年生たちの厳しい現実。初心者ゆえのハードルの高さも、描けて、もう少し深みが出せたのかなとも思います。
(参加者G) その弾けないもどかしさ、失敗した時のディテールもさることながら、もっと他の場面でも?
(斎藤) 終わったあとの反省。なぜ当たらなかったのか、どこが悪かったのか、身体全体の動きなど、工夫を重ねていく様子などが、近寄って撮れていればよかったのかなと思ってました。
(斎藤) 物理的な問題として、プレイゾーンには危険でもあり、絶対入れない。弓を引く手元やその表情など自分の撮りたい位置に入れない。ましてや大会となれば、その制約は多くなる。もちろん、事前にもっと安全な撮り方や、大会運営側との交渉など、やりようもあったのかと思いつつ、みなさんならどうしているのか?又、心理的な距離感、自分が入ることによって、プレッシャーがかかってはいけないし、プレーに支障が出ないようにするためには、どれぐらいの距離感で撮影をしていくのが正解だったのか。

(司会) 心理的距離感とはどんなことか、少し実際に実験してみましょうか。お二人に前に出てきてもらって、向き合って立ってください。そして、少しずつ近づいていって、これ以上無理だと思うところで止まってください。それぞれお互い、微妙な距離
を感じたと思います。10cm、30cm、ちょっとした差で近づける、近づけない、があっ
たと思います。それが「心理的距離」。さらに、これで目線を合わせてみて、そうする
と又、距離感が変わってくると思います。目が合ったときと、合わないときでも距離は
変わる、微妙なものですよね。(参加者0) 逆に私は距離感がいつも近すぎちゃって、距離の近い、主観的なものしか撮れなくて、客観的なものが全然撮れないなって、終わってから思うことが多くて。そうですね私は逆の悩みですね。
(斎藤) 主観、客観どちらも大事なんだと思うけど、やっぱり主観でずっと撮れるって羨ましい。
(司会) ふと気付くと懐に入ってる人っていたり、逆に絶対入らない人も。一定の法則があるようでない気もします。先ほどお二人に実験してもらいましけど、距離を意識した瞬間に微妙な空気が流れる。
(参加者T) 僕はあまり距離感を意識していないですね。取材の中で少しずつ距離が近づいてきたら、少しフランクに話しかける、そんな感じですね。ただ、撮りたいからわざと仲良くなることはないです。
(参加者H) 僕は基本的にあまり寄らず引きでいく方ですね。今回の映像で、先輩とのやり取りの様子をしっかりグループで押さえていたところが良かったですね。自分と向き合う、という意味で、一人で悩んでる姿や、後ろ姿を捉えたカットがあると、距離感としても、メリハリも出て良いのかと。
(斎藤) 練習場所も限られていて、チーム練習がほとんど。なかなか一人のシーンが難しかった。皆、個々苦労して練習しているので、狙いたかったのですが・・。
(参加者M) 一人になる瞬間、そこにどれだけアンテナを張っていられるか、個になる瞬間がきっとあるはず。チーム練習を狙いながら、横目で見てその瞬間に、レンズを向けていく、少し退いた距離感から、一気に近づいていく形とか。
(司会) 最近の学校取材の難しさもありますね。時には、チーム取材はOK でも、一人の選手に注目するような個別取材はしないでください、とか。プライベートに関わる部分となればなおのこと、それらの制約も距離感に自ずと影響が出てしまう。そんな難しさもありそうですね。
(参加者N) 最後に高校生3 人が悔しがる場面。その悔しさの背景をもっと描いて欲しかった。練習では上手くいっていたことが、できなくて泣いたのか、悔しさの理由がもっとわかると。
(斎藤) 1 年前の新人戦では優勝したが、この大会ではたぶんダメだろうという予測はあった。泣いたあとすぐに女子控え室のほうに入ってしまったため、そこは追いかけず。感情がすごく動いたところだったと思うので、もっと深掘りできたらよかった。
(司会) ボロボロ涙を流すシーンが印象的なだけに、あのときコーチが何を語っていたのか、もっとはっきり録音できていたら、涙の理由も少しは見えてきたのかも。雨の中、技術的には厳しい条件かと思うけど、まさにそこも距離感の問題にリンクしてきますね。
(斎藤) 貴重なご意見頂きありがとうございました。いろんな方からフィードバックしていただいて、すごく勉強になりました。現場に活かして行きたいと思います。
第二部 今一番輝きを放っている先輩カメラマンに聞く、イケてる映って何?

「秋田内陸線とともに」
﨑野 哲平(NHK 秋田)福岡の民放で4 年半カメラマンを務めたのち、2 年前にNHK に転職。
【V 視聴・概要】
視聴者からの投稿から、秋田内陸線を花で応援したいと、一人ダリアを沿線に植えている男性を取材。
【トーク】
(参加者M) 全体的に色が鮮やかでダリアの花が映っているシーンがとても印象的。ダリアを育てる方の人柄が気さくな方で、近寄りやすい方、ダリアの花とセットでとても理解しやすかった。
(崎野) 主人公の方は気さくですが、言葉数少なく黙々と作業するタイプ。地元の人との絡みが撮れたので、ただの寡黙な人にならずに済んだのかな。そのあたりが伝わってるならよかったです。
(参加者O) シャポン玉のスローカット含め、とても印象的で、その人の生き様、人生も感じられた。
(崎野) 今ドキの言葉で言えばで“映える”シャボン玉を編集上でもピークに持ってきたかった。そこまでに、この人がなぜ、どんな思いでやっているのか、しっかり伝えた上で見て欲しかった。全体の中で僅か1 分半ぐらいのシーン。少しでも見え方が変わればと。
(参加者P) 後半、地域全体への思いが綴られる。ダリアを起点に、笑顔の輪が広がっていく、すごく幸せな気持ちになりました。列車で手を振っている人もすごく笑顔で、最後ハッピーエンドみたいなところも私は好きでした。
(参加者C) 冒頭がとても静かな始まり、朝早いことも伝わってきてとてもよかったです。
(崎野) 早朝、誰もいない時間帯に奥から歩いてきて、そこの畑に向かっていく、あの地域の全体の空気感を、朝、電車が走って行く風景の中、誰にも見られずに作業しているところを、見せたいと思った。
(参加者A) 美しい映がいっぱいあって、機材が気になったのですが。
(崎野) カメラは普段ニュースで使用しているZ450 です。ガンマ設定で、やり過ぎない程度、少し色みを変えて撮っています。特機やズームなどは極力使わず、FIX 重視で撮りました。又、シャボン玉のスローは、シャッタースピードを上げて撮っています。編集で3 倍6 倍程度スローにしたときに、映像が流れずに済むので。
(参加者I) 冒頭、何だろう、ドラマみたいな映だと思って、これから何が起きるのか期待感が高まった。一方で、人によってはゆったりする感じもあって、そこで止めてしまう人もいるかな、とも思いました。
(崎野) 若い人が見て、主人公の登場まで、30,40 秒かかる映像に着いてこれるかどうか。そこが課題、カメラマンが映像にこだわらなくなると良くないですし、ただの自己満も然り、その瀬戸際がすごく難しいと。
(司会) 映像の内容が、見てパッと理解できるものか、それとも難解なものかによっても、感じる長さに違いもありそう。その映像に共感できるかどうか、も大きいですよね。この早朝の青さに、キュンとなるかは、その人の原体験にも左右される。あの映像から、雨上がりの匂いまで感じとって「いいなぁ」と思うか、それとも「なんで青いの?」と思ってしまうか。
(参加者G) 突然、父親の写真が出てきたシーンがありましたが、おそらく事前の構成や台本の中にはなかったことかかと思うのですが、どんなことを考えて撮影したのか、予想していないことが起きた時の心情は?
(崎野) 別の写真を待ってたので心構えはあった。どんな写真が出てきても撮ろうと。写真そのものよりは、出してきてくれた思いの部分も、まずは撮って、その意味づけは後で考えれば良いと。全てを想定できるわけでなく、常々想像はしながらも、想定外は起きるもの。まずは変に頭は使わず、その場で起きていることをしっかりと撮りきることを目指す。むしろ予定調和なインタビューではなく、ふとしたときに出てくる、つぶやきのような言葉をしっかり撮っていきたい。

「特別な世界 囲碁に魅せられて」
【V 視聴・概要】
今年3 月に開催された囲碁の高校選抜大会で一年生ながら女子個人の部で優勝した秋田の高校生を主人公に、その彼女がのめり込んだ囲碁の世界を描いたのリポート。
【トーク】
(崎野) 冒頭でいかに人を惹きつけるか。多くの人にとって囲碁は遠い世界。そんな中、実力を持った女子高生が秋田県にいるということが、囲碁を近づけるチャンス。少しでも格好良く興味を持ってもらえたらと、照明も使って、1分近く見せることにした。上手くいっているかどうか。自己満足に終わっているのか。
(参加者S) 冒頭、率直に格好いいなって思いました。顔も見えないまま、一瞬見える制服に、この人は誰だろうとか、勝手に想像して。囲碁将棋の取材にも行ったことがあるけど、本当にパチパチ打つだけで、どう撮ったら良いのか、悩んだときもあって、あとで女子高生が出てきて、そのギャップも素敵だと思いました。
(崎野) どこまで隠すか、制服だけちょっと見せるのか、本人を出してしまうのか、囲碁に集中してもらうか、人か、否か、事前に構成も、絵コンテも、いろいろ考えて撮りました。
(参加者G) 囲碁盤の下から撮ってるのか上から撮ったのか分からないですけど透明なところに打っているところ。ドラマっていうよりは、1 つの映像作品、ドラマ10 のタイトルか、のような躍動感があった。
(崎野) ガラス板にペンで描いて、囲碁盤のように打ってもらい撮影した。なんとか囲碁の面白さを映像でも表現できたらと思って、このカットは間に挟み込みました。
(参加者V) お母さんへのインタビューはあらかじめ、あのタイミングを予定していたのですか?
(崎野) お母さんはもともと嫌って言っていた。その日は娘の誕生日で、手の込んだ料理をしている時で、申し訳ないと思いながら、流れで、なのでお母さんが映っているのは一瞬、あとは全部写真でかぶせています。構えて撮ることでもないと。日常の中でさくっと、軽い感じで聞くにはあの感じかなと。
(参加者F) カメラは何を?
(崎野) FX6 という大判センサーカメラです。基本的にZoom に頼らず、カメラ自身を動かして撮り、奥行きとか、ボケ感をレンズで調整しながら撮影しました。一部、スライダーも使って。効果的に使えたかどうかは別として、スライダーを人ものドキュメンタリーで使えたのは大きい収穫だった。大きいカメラでは難しい表現ができたし、囲碁の会場はけっこう密接なので、ローアングルで撮ろうとか、回り込もうとしたときに小型であることはメリットでした。
(参加者S) いろんな最新の映像機器に興味もあり、番組で使えそうな時は果敢にチャレンジしてくんですけど、まずは使ってみないと、分からないので経験値を高める意味でも、必要ですし、その特性を知ることも大切ですね。
(司会) ちなみにその引き出しを多くしていくためにどんなことをすれば?
(参加者S) 普通にYouTube や映画を見たりします。あと調べて知っているだけでは、実践時に苦労することが多いので。前もってあらかじめ空いた時間で練習して、その機材の個性を生かすも殺すも、自分次第なので。
(崎野) 僕はCM をよく見ていて、見せるための工夫がたくさんあるので、どうやって撮ったのかなとか、調べたりすると、意外とメーキング映像も出回っているので、見て勉強していますね。
(参加者N) 若手の方っていろんな機材を使いたがるけど、結局、フィックスが決まらないとやっぱり映像って僕も駄目だと思うんですよね。まずはフィックスがちゃんと撮れるようになってから、そこが大事かなと。
(司会) あくまでツールでしかない。最終的に伝えたいものがしっかりした構図で撮れるようにならないと、道具に溺れる、自己満になってしまう。挑戦、テストという意味では実戦してくべきですが、結果、効果的だったのか、という振り返りも忘れずに。
結びにかえて

今回は「思いが意図的に伝わっているのか、特に若い世代たちに」という点が3 人の中での共通テーマでした。本当に伝えたいと思った時に、使えるツールがない、伝えるスキルがない、ことが一番カメラマンとしては辛いところ。日々の学びとスキルUp、一人でも努力できることではありますが、こうして集まって知恵を出し合うことも、面白いと思っております。今後も引き続き学びの場の提供をしていきたいと思います。ありがとうございました。(文責:百崎)